化石
岩波新書 1968
井尻さんの家に伺って、言葉にしにくい熱いものに包まれた。日本家屋のなかの一室で、そこが書斎にも応接間にもなっているのだが、壁一面に書棚のような棚が取り付けられていて、そこに古ぼけた菓子箱のような紙箱や木箱がぎっしり並んでいる。そのすべての箱が化石標本なのである。いくつか開かせてもらったが、ほんわりとした綿に包まれて、見たこともない化石がそれぞれ黙って眠っていた。南方熊楠が天皇に献上した粘菌標本の菓子箱もかくやと想わせた。
すでに井尻さんには築地書館の数々の本(「人と文明」シリーズや古生物学や地質学の本)などを通して、親しみを感じていたので、会いたいと電話をしたときは、会いたい理由を説明するのに苦労したのだが、井尻さんのほうが何かをすぐに察して、ああいいですよと言ってくれた。
実際に会ってみると、表情も会話も柔和なのだが、こんなに厳しい人物だとは想像がつかないほど裂帛で、厳正な目を社会に光らせていることが5、6分で伝わってきた。昨今の学問、研究、その出版、そのメディア化(たとえば雑誌特集やテレビ番組)に対して、ことごとく問題を感じているようだった。いや、そういう話をしっかりしたわけではなかったのだが、そういう気概で社会を見ていることはすぐ了解できた。ぼくが28歳のころのことである。
井尻さんに会いにいった理由は、もうひとつあった。井尻さんは吉田一穂の詩の傾倒者であって、研究者なのである。化石学者がたんに詩が好きだというのではない。一穂が『古代緑地』や『黒潮回帰』で直観した地質学的宇宙観に共鳴して、自身の視軸を一穂とともに思索しているというふうなのだ。ぼくも大の一穂ファンで、ささやかな化石少年だった。井尻さんに会いにいかずにはいられなかったのだ。
化石は英語では〝fossil〟という。これはラテン語のフォシリスから派生した言葉で、発掘物という意味である。だからフォシルには「石化する」という意味はない。
それが日本語・中国語の「化石」では石という文字が目立つので、化石といえばどうしても石に入った古生物をイメージしてしまう。実際には、大昔の生物たちが残していったものなら、石に入っていようといなかろうと、すべてフォシルなのである。だから大別するときは、トレースフォシル(生痕化石)、コープロライト(糞石)、ケミカルフォシル(化学化石)、ボディフォシル(体化石)に分ける。
逆に、石に刻まれた記録だからといって化石とはよばないものも少なくない。日本の戦後の化石学や地質学は井尻さんと、そのころ北大にいた湊正雄さんが牽引してきたところが大きかったのだが、その井尻・湊よりもうひとつ前の大御所だった矢部長克さんという長老がいた。あるときその矢部大先生が井尻・湊の二人を呼んでテストをした。見慣れない岩石を2個見せて、「これは何の化石と見えるかね」と聞いたのだ。二人はまったく見当がつかずに兜を脱いだところ、大先生はニヤニヤして「ぼくが見るところ、こっちは氷の結晶の化石、こっちは隕石が水面に落ちたときの衝撃波の化石じゃないかと思うんだ」。
かくも石とはすごいレコーダー(記録者)であるというエピソードだが、このように石に残った自然の記録は厳密には化石とはよばない。乾痕・雨痕・漣痕などといって、化石とはべつに区別する。化石はあくまで動植物のドキュメントなのだ。
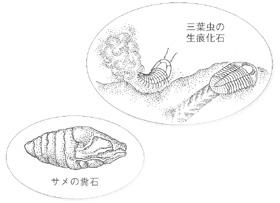
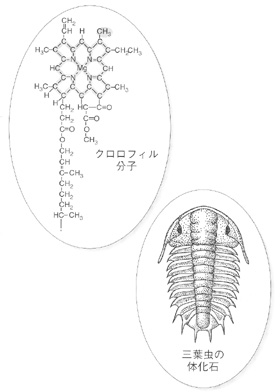
本書はこうした話を交えながら、しだいに化石研究の真骨頂がどこにあるかを案内していくのだが、新書でありながら井尻さんの厳正科学主義といったエッジが鋭く立ち上がってきて、なんだか化石の前に端座させられた気分になる(あの日はたしか、ぼくも井尻さんの家では正座しつづけていたように記憶する)。
化石の解読には、多分野の研究成果がアッセンブルされなければならない。化石が示すのは古代のウマの臼歯だけだったり、恐竜の爪跡だけだったり、ときには毛が1本だけ残っているということだってある。それを相手に10万年前や1000万年前や3億年前の「生物社会」を再生しようというのだから、それには岩石学や地層学はむろん、歯学も花粉学も、植物学も動物学も進化学も潮流学も気象学も、ウンコ学も解剖学も、ほとんどの学問が総動員される必要がある。
本書のころはまだ成果がほとんどなかったのであるが、最近では化石からDNA鑑定することも可能になってきたので、分子生物学や遺伝情報学は化石学には切っても切れないものになった。
井尻さんはこのように化石をめぐって自然科学の総体が大きく動いていくということを、当初から察知していた。その大きく動く科学ムーブメントを日本におこそうとしていた人だった。地団研(地学団体研究会)の活動もそのひとつだ。
著述活動も広にわたる。刊行順にいうと、『古生物学論』(平凡社)、『マンモス象とその仲間』(福村書店)、『自然と人間の誕生』(学生社)、『お月さまのたんけん』(麦書房)、『地球のすがた』(偕成社)、『人体の矛盾』(築地書館)、『文明のなかの未開』(築地書館)、『ぼくには毛もあるヘソもある』(新日本出版社)など、子供向けも文明人向けも含めて、かなりのペンをふるってきた。
本書では、とくに後半でアリストテレスからヘッケルまでを辿って大きな問題提起をしている。ヘーゲルの『精神現象学』を紹介して、脳という物質的な系によって人類が過去の物質と生物をめぐる歴史を把握したことをもっと一貫した論理で考えるには、今日の科学にはいろいろおぼつかないところがあるといったくだりは、その後に井尻さんが『弁証法をどう学ぶか』『弁証法の始元の分析』(大月書店)といった著書を世に問うたこととあわせて考えると、とても大きな構想がそこにはひそんでいたのだということを思い知らせてくれた。
いま化石学はいちじるしい飛躍を見せている。化石学や古生物学では年代層を岩石の模式断面で測り、その層序の中に地質年代の“瞬間”を見いだすことをゴールデンスパイクというのだが、このゴールデンスパイクが井尻さんの時代にくらべて格段に正確になり、格段に情報量をふやしているのだ。
タフォノミー(taphonomy)も発達している。タフォノミーは生物が死んでから岩石や堆積物のなかで発見されるまで、どのような出来事を“体験”したかという、いわば“死後の物語”を研究する分野なのだが、これが俄然おもしろくなってきた。
ダイアジェネシス(diagenesis続成作用)という研究も浮上している。生物がどのように埋没し腐敗していったのか、それが最初はどの地点、どの時点での出来事で、それがどのように運搬され破砕されたのか、そこにどんな物理変化や化学的変化が加わったのか、そういうことを研究するのである。これは従来の進化生物学では考えられないほど情報編集的だ。
そうなのだ、いまや化石学は“古情報学”とでもいうべき華麗な時代を迎えつつあるのである。しかし、ぼくとしては井尻さんの書斎に正座したときの、あの菓子箱の砲列から感じた言葉にならない畏怖をこそ忘れたくない。化石は情報なのであるが、そこにはまだ言葉にできない情報が潜んでいる。

両生類と爬虫類の寄せ集めのような特徴を示しているという
化石についての本は実は鉱物本よりずっと多い。最近の普及書では、ジョヴァンニ・ピンナ『世界の化石大百科』(河出書房新社)、ニコラス・ウェイド『化石は愉しい』(翔泳社)、日本古生物学会『化石の科学』(朝倉書店)などはどうか。日本にも化石はけっこう多く出土するので化石採集をしたい向きには、ハンドブックとして浜田隆士・糸魚川淳二『自然観察シリーズ・日本の化石』(小学館)、小畠郁生監修『ポケット図鑑・日本の化石』などが手頃だ。



