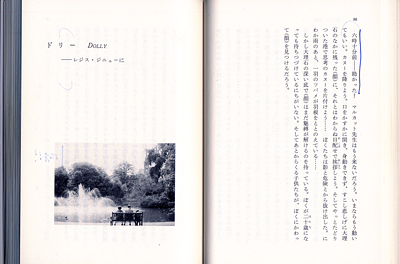父の先見


岩波文庫 2005
Valery Larbaud
Enfantines 1918
[訳]岩崎力
年の瀬だ。往く年がもぞもぞしたものに見えてきて、来る年が少しそわそわしたものに感じられてくる。
年初に何を千夜千冊しようかと物色していた。ちょっとばかり気分を変えて、ぼくに「方法の秘密」をもたらしてくれた書物たちを(これまでもたくさんあったけれど)、あらためてとりあげたい。ただ、うんと遠いものを見つめたい。そう思って、自分がどのように秘密に気づいたのか、少しさかのぼっていた。
そうしたら、急に少年のころのことがあれこれ思い出され、そうだった、ぼくは「方法の秘密」のきっかけをすでに少年時代に感じていたのだと思い至った。そうしたら、あの本がその秘密をぼくに代わって書いてくれていたことがリマインドされた。よしよし、あの本がいい。あれはぼくに「少年であることの苦み」の意味を発足させてくれたのだ。ヴァレリー・ラルボーの『幼なごころ』である。2年前、やっと岩波文庫に入って、手に入りやすくなったこともある。
ぼくは子供のころに、何度か「大人になる危険」を感じたことがあった。とくに大人たちが何もおこっていないのにワッハッハと笑ってみせること、どうでもよいような相槌を大げさに打ち合っていること、まるでついでのように子供に注文や注意をすること、そのくせこれらのあとは急に何もかもがなかったような普通の顔をすること、こういうことを見て、「これは大人になるのはまずいぞ」と思ったのである。
ラルボーがそのことをちゃんと書いていた。「ずっと昔から大人たちの会話を聞くと私は悲しくなり、自分が自分から遠ざかるような気分になる。私が喜んでつきあうのは、ひどく内気そうな男の子たちや、このうえなく優しい少女たちだけだ。自分の人生がそういう子供たちにとりかこまれ、かれらのまなざしの前で過ぎていくのだったら、と私は願う」。
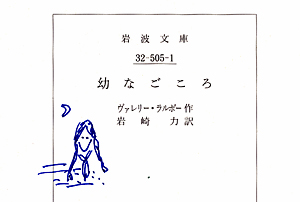
ラルボーのことは、フランス文学派の連中にさえあまり知られていないかもしれないが、とんでもない作家だった。少年少女の心の動きを描いては、他の追随を許さない独自のものがある。その質感の精彩はきわめて知性の高いものがもたらしていて、加えて極限まで文体と文脈が練られたものばかりだ。
それが悠遊閑適、極上の逸品なのである。ところが何が理由かは知らないが、これまでずいぶん誤解されてきた。
長らくラルボーは「小さい作家」と言われてきた。8歳から14歳までの少年少女を主人公としてきた作品が多いからであるし、ラルボー自身が大作家をめざしていなかったからでもある(大作家というものを拒否しつづけた)。しかし、「小さな作家」という評判ほどラルボーを誤解させるものはない。そういう形容はまったく当たらない。
なにより、たぐいまれな知性と構想とセンスをもっていた。それをどうやって説明していいか、ぴたりとした説明がしにくいのだが、たとえばジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』のフランス語訳はラルボーの仕事だったといえば、少しは伝わるだろうか(ラルボーは、貧窮のジョイスに自分の留守中のパリの自宅を無償で提供していた)。
また、たとえばバルナブースという破天荒な主人公を設定した『A・O・バルナブース全集』(岩波文庫)という作品があるのだが(ラルボーの処女作集)、これは南米の“富裕なアマチュア”が架空の全集を作ったという人を欺く設定だったといえば、ラルボーがボルヘスに先立つ「知のサーカス」の名うての演出家であったことが伝わるだろうか。ラルボーは各国語に通暁した語学の天才でもあったのだ(子供時代からヨーロッパ各地を両親とともに旅行していた)。
言葉の本来を動かせる達人なのである。登場人物の文字の綴り、言葉がもつ音のフィーリング、事物のもつ言葉の意図、文脈にひそむ言葉の鍵と鍵穴の関係を、ほどよい抑制と速度を効かせながら、ふんだんに操っている。
だからといっていたずらに技巧には走らない。あくまで登場人物たちの「香ばしい失望」をのみ、言葉にしつづけた。だからそれが少年少女に向かったときには、他の追随を許さなかった。
ぼくはジャン・コクトーの『怖るべき子供たち』を読んだとき、ほとんど息が詰まるほどの衝撃をうけたけれど、それがラルボーの『幼なごころ』のあとに書かれた作品だったということを知って、そうか、ラディゲもコクトーもラルボーの変形だったのかと得心したものだった。
2007年劈頭に贈る『幼なごころ』には8つの小篇と二つの補遺が並んでいる。いずれも「ラ・ファンジュ」か「NRF」に発表したもので、当時すでにアンドレ・ジッドがぞっこんだった。
順番に読むのがいいだろうが、びっくりしたいのなら傑作『包丁』から読むことをお薦めする。『失われた時を求めて』を書きつづけていたマルセル・プルーストがこんなことを書いている。「『包丁』を読んだときの感動があまりにも強烈で、1年以上たった今でもまだ少し胸が痛みます」。
ミルーはジュール・ヴェルヌが嫌いな少年である。それより嫌いなのは、大人たちがくだらない話題と冗談を交わして、「では、また」「それじゃ、また」という日々をくりかえしていることだ。ミルーはそういう大人たちをよそに、ダンバとローズというごく小さな「目に見えない友達」とばかり語りあっていた。
ダンバは水面に反射する日の光に姿を隠す名人で、そのときはたいていフランス国旗をはためかせて未知の領域に進軍していく。ローズはアラブ人にさらわれてきたちっちゃな少女で、どの舞踏会にも必ずいる一番気になる女の子に似ている。ミルーはそういうダンバとローズと一緒に、おばあさんがイエズス会の歌をうたうのを聞くのが好きだった。
ミルーの家には小作人の娘のジュリアが住んでいた。12歳になったばかりで、いつも靴下の繕いをさせられていた。ミルーには、おしゃまなジュリアをからかうことが一番好きな遊びだった。そこへ羊飼いの少女ジュスティーヌが連れられてきた。おばあさんがイングランドから引き取ったらしい。短い金髪は編んではいなかった。ミルーはその子の薬指に傷痕があるのを見て、どぎまぎした。
ある夜、ミルーはジュスティーヌのために『包丁のみじめさ』というお話をつくろうと思った。言葉を紡いでみると、何もお話になってこない。そのうち、詩というものをめざすようになってきた。ジュスティーヌは詩そのものなのだ。けれども毎晩、毎晩、その詩を想ううちに疲れて寝入ってしまった。
こうして、その日がやってきた。誰にも計画を知られないようにして、ミルーは台所に入り、流しのところへ行って包丁を手にとった。ジュスティーヌの薬指の傷を目に浮かべ、それから目を閉じて、重い包丁をそっと手に落とした。たちまち血が流しに垂れた。ミルーは慌てて洗面器に水を入れ、手をそこにつけた。蛇口から流れる水は血を洗い、ミルーの薬指の先の爪がはがれていることを示した。
休暇がおわって、手に包帯をした少年は少女と別れた。少年を乗せた馬車がゆっくり動きだすと、父親がいつものように理不尽な言葉を浴びせた。馬車は説明ができないものばかりを乗せていた。
だいたいはこんな話だ。筋書きだけでは何も伝わらないだろうけれど、なんとも溜息が出る。実際にはこの筋書きの前後にいろいろ“素知らぬ話”が加わっている。その“素知らぬふり”もいい。
読みおわった者には、ジュスティーヌの薬指の傷痕に合わせたミルーの包丁の静かな落下だけが、いつまでもこだまする。そういう作品だ。プルーストが「一年以上たった今でもまだ胸が痛みます」と書いたのがよくわかる。
フランス語では「幼なごころ」はアンファンティーヌ(enfantines)という。この語感がいい。アンファン・テリブルといえばコクトーの「怖るべき子供たち」だ。大人が想像できない子供たちである。
ラルボーが綴るアンファンティーヌは社会の隙間に出入りする。メインのところでは気がつかれにくい。そういうアンファンティーヌの本質は「よそ」(余所・他所)のどこかに秘められているものなのだ。そこを子供は見抜くのだ。子供が社会に対抗しているのは当たり前だが、ラルボーの子供たちはその社会にはいっさい所属していない。そういう子供が発見するアンファンティーヌなのである。ぼくもまたそれを、『花鳥風月の科学』(中公文庫)や『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)で、「よそ」や「ほか」や「べつ」にひそむものと指摘した。
まさにそのように、ラルボーが綴る子供たちは、あたかも「生まれつき夕方の光のように想われる孤絶」のなかに戯れる者たちだった。「よそ」と「ほか」と「べつ」を知っている驚くべき「時分の花」たちなのだ。
それなら子供たちはいったいどこで“そのこと”に気がつくのだろうか。ラルボーははっきり言っている。“そのこと”は集団のなかの何人かの子供たちが信号を発しているのであると。
どんな国のどんな町や村にも、一番背の高い子や一番背の低い子がいるものだ。あるいはまた、一番髪の毛が長い子、一番虫取りが上手な子、一番リボンが大きい子、一番スカートが変な子がいるものだ。それだけでなく、遠足に一番貧しいお弁当をもってくる子、みんなが楽しいときに最初に顔を俯ける子、一番笑わない子、一番きれいな子、一番声のいい子、必ずそういう子がいるものだ。
アンファンティーヌ=「幼なごころ」とは、そのような集団のなかで“ちょっと突起している子”を、別の子が自分はその子の唯一の崇拝者であると認知したとたんに(必ずそんなことを感じたのは自分だけだと思いこむ)、動きだすものなのである。
大人たち、とりわけ両親というものは、「お前もそろそろみんなのようにならなくちゃね」と言う。しかし「幼なごころ」とはその「みんな」という平均とはおよそ異なる「突起」や「よそ」や「べつ」からやってくる。風の又三郎のように、転校生が幼ない物語の主人公になりやすいのは、そのためだ。
少年少女は、この平均を破るものの秘密に格別の関心がある。ふつうに元気なジュリアをからかうミルーが、新参のジュスティーヌの傷ついた薬指に秘密を感じるのは、そのせいである(ぼくは、いとこの眞智子の長くて細い指が長い髪をかきあげる素振りに神秘を感じた)。
けれども、そのような「小さくて青い光のような美しい異様」への関心は、ときにひと夏で、せいぜい14、5歳のときにおわってしまう。そのせつなさはどんなものにも譬えようがない。どんなものにも譬えられないから、その例外的な「よそ」や「ほか」を運んできた子の憂いとともに、その記憶が刻印される。記憶が存在学になってしまうのだ。
いったい、このような「幼なごころ」の発生と成長と消滅というものは、われわれの人生のなかの何を暗示しているのだろうか。「幼なごころ」の消長は、われわれに何をもたらしたのか。
ヴァレリー・ラルボーは、そのことを「幼少年期を取り戻せないわれわれ」が頻りに思い、その解明に没頭することだけが、文芸や音楽や、恋愛や政治や、絵画や遊蕩の本質だろうと見抜いたのである。とりあえずは、このような説明ができるのだが、けれどもこれだけではまだ5分の1くらいのことしか言えていない。“突起の子”を感じる「わたし」のほうにも秘密があるからだ。
本書の冒頭に『ローズ・ルルダン』が収録されている。田舎の寄宿学校にいる12歳の少女の「わたし」が、ローザ・ケスレルという美しくて賢い別のクラスの少女の噂を耳にしたところから、話が始まる。彼女は「レーシェン」(ローザの愛称=小さな薔薇という意味)と友達から呼ばれていた。
この「わたし」は叱られるのが好きだったのである。叱られたくて、禁じられていることをわざとするような気持ちがどこかにあった。食卓についたときの行儀を先生から叱られたとき、書き取りの点がよくてずるをしたでしょうと詰られたとき、悲しいのだけれど、その悲しさをじっとこらえるのが好きだった。
ラルボーは、綴る。「仮面のような顔の裏側を通って、目から心臓に落ちていくように思えるあの涙の味が好きでした。宝物のようにそれを拾い集めていました。一日の旅の途中で出会った泉のようでした」。
それがいつのときからか、レーシェンのことを想えば、その悲しみが和らぐようになっていた。それはもっと幼かったころ、オールド・ティーローズが好きだったとき、その血の一滴がいとおしくなったことに似ていた。「わたし」はいつしかレーシェンに気にいられることばかりを考えるようになった。先生が「医務室に行く人?」と言ったとたん、胸が早鐘のように打つのである。
こういう少女独得の「わたし」感覚は、男の子にはきっとわからないだろうと思われているようだ。が、そんなことはない。そこをラルボーは解明して描写する。たとえば、「わたし」はレーシェンの本名のローザ・ケスレルの綴りや音に似せて、自分の名前をローザ・ルルダンと綴ったりする。たとえばレーシェンの上っ張りを心臓が飛び出るような思いで、ほんの数秒だけ羽織る。
こういう場面は、アンファンティーヌにとって、そもそも「身近か」とは何かという本来を告げている。太宰治が『女生徒』(角川文庫)で試みながら、描ききれなかった感覚だ。アンファンティーヌとは、身近かなるものの何に震えられるかをいちはやく選ぶ「自分が壊れる寸前の能力」のことなのだ。子供たちは誰と身近かになりたいかを、すぐに決められる。好き嫌いがすぐ決まる。けれども、そう思えばおもうほど、どぎまぎしてしまう。どうしていいか、わからない。それでも自分勝手な親密感だけは大きくなっている。
この感覚にはいつしか必ず“軽い撃鉄”が落とされる。それはしばしば「空が見たいのに、窓ガラス一枚一枚に白い紙が貼られていく」ようなことに近い。「わたし」のばあいは、レーシェンからある日、「変な子ね」と言われたことで、その撃鉄が落ちた。たった一言、「変な子ね」と言われただけなのだ。ところが、ところがだ。「わたし」はその言葉がほかの子の誰に対しても発せられたことがなくて、自分にこそ向けられている撃鉄だろうことが確信できたとたん、むしろ「変な子」を演じつづけることになるのである。
余談になるが、こういうアンファンティーヌの「きわどい撃鉄」が理解できるなら、実は「いじめ」などという問題は、その発端にかぎっては、いじめられた子がひそかに望んだものだったかもしれないことすら予測できるのである。
ラルボーを読んでいると、たいていの昔日の甘美な記憶というものがフラジャイルな撃鉄によってもたらされていたことが見えてくる。
ラルボーはそういう「わたし」を通して、少女や少年にひそむアンファンティーヌがきっと「逆光」や「まちがい」をもとにしていることを、すなわち「想わせぶりだけが少年少女の少年少女たる日々の本質」であったことを告げてくれた。
ところで、ぼくが「幼なごころ」をどう綴ってきたかは、あるいは少しくらいなら知る人もいるかもしれない。20代後半には、稲垣足穂に倣って「芸術は幼な心の完成だ」と言っていた。それが30代には「存在の本質は幼な心にある」にすすみ、40代になって、「ぼくは幼な心を編集しつづけている」になってきた。いま思えば、どれも似たりよったりであったけれど、ひとつ心残りだったのは、ヴァレリー・ラルボーのように、そのことを小さな作品にしてこなかったことだ。
いや、筑摩書房の藤本由香里さんとは(『フラジャイル』の担当者)、そのあたりのことを『ケミストリー』という仮称のタイトルの一冊にする約束をしているのだが、そして、その草稿を少しは書きはじめたのだが(25枚くらい)、そのあと何ということか、「ケミストリー」というバンドが流行したり、ぼく自身が「千夜千冊」にかまけたりで、これはいまなお放ったらかしになっている。そのうちぼくの“気分の包丁”が蘇ってくるときがあれば、また執筆を再開することもあるだろう。
なんだか、正月のための年頭の課題をメモしているような話になってしまった。今夜はこんなところで店仕舞いだ。ラルボーの言葉を引用して、今年の劈頭の千夜千冊にあてておく。「私は、この歌がごく僅かな人々にしか聞こえないことを願っている」。