父の先見


ポプラ社 1982
銀河ステーションは「億万の蛍烏賊(ホタルイカ)の光をいっぺんに化石にして空に沈めた」というぐあい、「幻想第四次の銀河鉄道」の汽車の姿は「夜の軽便鉄道」そっくり、線路のへりには「芝草のなかに月長石ででも刻まれたような紫の竜胆」が咲いている。
車室は黄いろい電燈がぼうっと並んでいて、腰掛は青い天蚕絨(びろうど)が貼ってあり、壁には真鍮の大きな二つのボタンが光っている。車窓の「向こうの河原は月夜」になっているらしい。そこに乗っていたカムパネルラは円板状の「黒曜石でできた地図」をぐるぐるまわしている。天体鉄道図だ。
ジョバンニが「いまぼくたちが居るところ、ここだろう」と指さしたのは白鳥座の停車場。「二〇分、ていしゃー」の合図で降りてみると、改札口は水晶細工の銀杏に囲まれ、幅の広い道が銀河の青光の中に通っている。そこに近づくときらきらとした川が流れ、「銀河の水が燐光あげてちらちらと燃えるように」見えてくる。
その先の崖の下はイギリス海岸のように白い岩でできていて、そこに「プリオシン海岸」という瀬戸物の標札が立っていた‥‥。

御存知、『銀河鉄道の夜』の目映い光景である。
その美しさに眼を奪われているとわからなくなるのだが、この物語には、少年の心にはすぐは見えないような驚くべき特徴がいくつも含まれている。
なんといっても銀河鉄道は「死者の列車」であって、カムパネルラは「死者」なのである。いや銀河鉄道に乗り合わせた乗客はすべて死者なのだ。それどころか、この鉄道は死後の銀河をめぐっていた。
そもそも『銀河鉄道の夜』においては、この目映い銀河鉄道の場面は「六、銀河ステーション」以降の光景であって、物語はそこに至るまでに「一、午后の授業」から「五、天気輪の柱」まで、まったく別の場面を展開させている。そこで、一転、銀河鉄道のファンタジーが奏でられる。けれども、ジョバンニが夢からさめると、カムパネルラが川に落ちた少年を助けようとして死んでしまったという話になる。
この構造はやさしくない。
だいたいジョバンニはカムパネルラと齟齬が生じた関係になっている。少年独特の“束の間の疎遠”というものだ。物語はジョバンニが活版所で働き、お母さんに牛乳を運ぼうとしたり、ケンタウル祭の夜の時計屋でアスパラガスの葉に飾られた星座早見を眺めたり、ザネリにからかわれたりしているものの、カムパネルラとはまったく口もきいていない。なぜかジョバンニはカムパネルラを避け、カムパネルラはそのジョバンニの気持ちをわかっているふうだ。
そのカムパネルラが“束の間の疎遠”の真っ只中、事故で死んでしまったのである。物語はカムパネルラの謎の死を知らせないまま、天気輪の柱の下の冷たい草の上に寝転んだジョバンニが、うつらうつらと遠くの汽車の音を聞きながら眠りこみ、「銀河ステーション、銀河ステーション」という声がして眼がさめるところから、さっきの銀河鉄道の目映い光景に入っていく。
冒頭は、先生が黒板に吊るした星座図の天の川を指しながら、「この川とも乳の流れたあとだとも云われている白いものは、ほんとうは何ですか」と聞くところから始まっていた。童話文学あるいは少年文学きっての名場面だ。
先生に当てられたジョバンニが立ってみると、天の川が何かを急に答えられなくなっていて、先生がさらに聞くたびに真っ赤になる。そこで忘れられない描写になっていく。
「ジョバンニの眼のなかには涙がいっぱいになりました。そうだ僕は知っていたのだ。勿論カムパネルラも知っている、それはいつかカムパネルラのお父さんの博士のうちでカムパネルラといっしょに読んだ雑誌のなかにあったのだ。それどころでなくカムパネルラは、その雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から巨きな本をもってきて、銀河というところをひろげ、真っ黒な頁いっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした」。
どうやら、この一冊の「巨きな星の本」の中で、ジョバンニはカムパネルラと銀河鉄道の旅をしたようなのだ。物語のなかでジョバンニとカムパネルラが銀河の旅をするのは、ここだけなのである。
あとは教室でジョバンニが立ち尽くし、カムパネルラも親友の気持ちを慮って手をあげないようにし、ジョバンニがお母さんを思って活版所で働き、ジョバンニの夢の中で銀河鉄道の旅が繰り広げられ、そしてカムパネルラが死ぬ。それだけである。
しかし、この削ぎきったような物語の顛末が『銀河鉄道の夜』を永遠にした。
いったい宮沢賢治はどのように『銀河鉄道の夜』を構成し、いまわれわれが読むような格好に仕上げたのか。
あとでもう少し詳しく指摘するつもりだが、この作品は実に10年にわたって構成と編集の手を加え続けられていた。それも大略4次におよぶ大幅な加筆訂正削除があった。驚くのは、冒頭の「一、午后の授業」をはじめ、「二、活版所」「三、家」はすべて第4次原稿の、それも最後の最後になって付け加えられたということだ。
ということは、最初の物語では現実と幻想は最終稿のようには分かれていなかったのである。実際にも第1次稿を読んでみると、紛失した原稿があるせいでもあるのだが、物語はまことに錯綜していて、銀河鉄道に乗っている場面と、天体を夢想している場面とがごちゃごちゃになっている。そのかわりジョバンニとカムパネルラの少年っぽい葛藤も多く描かれていた。
が、賢治は何年をもかけてそれらを次々に削除していった。そのうえで、別の場面と決定的なステージの区別を入れた。とくに意外なのは、最初の草稿ではカムパネルラは死んではいなかったということである。
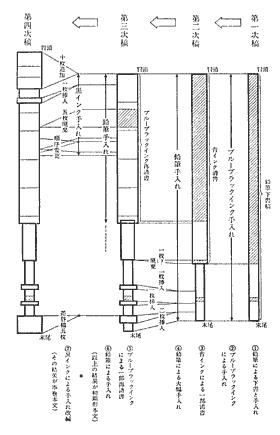
こういうことは、筑摩書房が総力をあげた『校本宮沢賢治全集』が多くの異稿をできるかぎり活字にしてくれたことによって、初めてあきらかになったことだった。
ぼくはその壮絶ともいうほどの編集プロセスの渦中を、入沢康夫さんや天沢退二郎さんを通して知って、なんだか“幻想月界王子”のような賢治がたくさんの顕微鏡の下で大小の検査光にあてられて、しだいに正体があきらかになってしまうのではないかという気持ちをもったことがあるのだが、実際には、そうではなかった。むしろこのプロセスで宮沢賢治はさらに複雑に、さらに精緻に光り輝いた。
その賢治について、賢治の童話を“イーハトーヴの星でできた鉱物の夢”のように読んでいる幻想的な読者には、ひょっとしたらあまり知られていないだろう話から、以下、書いてみる。
尾崎紅葉が『金色夜叉』の連載を読売新聞で始めたとき、賢治は6歳になっていた。
赤痢に罹って花巻本城の隔離病棟にいた。大変の病弱だ。風邪をひいたようね、それ、お薬、熱があるようだ、さあ寝なさいと大事に育てられすぎたせいである。
宮沢家は花巻一帯では「宮沢まき」とよばれたほどの代々の素封家である。父方は屋号をとって「宮右かまど」ともいわれた。母方は棟梁の家系だが雑貨商をしてから宮沢商店としておおいに発展して、花巻銀行・花巻温泉・岩手軽便鉄道の設立にかかわった。賢治はこういう家庭でタカラヅカ花組の主人公のように大事に育てられた。
その、弱虫で泣き虫の、過保護だった賢治がちょっと変わってくるのは、花巻川口尋常小学校の2年になったころからである。ススキの野原に火をつけ、小舟で北上川の対岸に渡って瓜を盗んだりした。これは、とてもよくわかる。これは、少年ニュートンや少年ヴィトゲンシュタインが火付けをして遊んだ「いたずら」そのものだ。これをしない少年なんて、大人になっても面白くない。
賢治はいつも誰かの影響をまっとうに受けとめている。3年の担任の八木英三先生からうけた影響は、五来素川が翻訳した『家なき子』を読み聞かされたことだ。八木自身が「私は噛みつくやうにこの少年小説を読んだ」と回顧していているほど、熱を入れたらしい。
最初に感動した童話が『家なき子』であったことは、ジョバンニがカムパネルラに寄せる微妙な感情にもよくあらわれている。賢治は泣きじゃくり、勇気を鼓舞され、八木先生の言葉をひとつずつを心に刻んだことだろう。だから、八木先生が黒板に「立志」と書くと、当時の少年なら誰もがそうだったのだが、その2文字に心を躍らせた。この時代のキーワードはまさに「立つ」。立志・立国・立身なのである。
いまはどうだか知らないが、ぼくが花巻に行ったときは朝の7時にチャイムが鳴って、賢治の『精神歌』が街に流れていた。歌詞はこういうものだ。
日は君臨し 輝きは 白金(はっきん)の雨 注ぎたり。
われらは黒き土に伏し まことの草の 種まけり
日は君臨し 穹窿に 漲りわたす青光り
光の汗を感ずれば 気圏のきみは隅(くま)もなし。

諸君、白金の雨の注ぐなかで「黒き土」となって「まことの草」のための種を撒きなさい。自身の意志に「光の汗」を流し、諸君は「気圏の者」になりなさいという歌詞である。遠野から下りてきて、花巻の宿でこのような歌詞であることを確認したときは、なんだか胸がつまってしまった。
大正10年(1921)、25歳の賢治は稗貫農学校(その後の県立花巻農学校)の先生になる。このあと辞任するまでの4年間は賢治が創作に熱中した時期だった。妹のトシを失ったのも、『春と修羅』『注文の多い料理店』を出版したのも、この時期である。その農学校に着任早々、賢治は『精神歌』を作って生徒に歌わせた。その歌詞はまさに八木先生が教えた「立志」であった。
こうして弱虫賢治は昆虫採集や鉱物採集をするようになっていく。小学校の教師の熱意は、必ずやこのような別の熱意を少年に発見させるものなのだ。
よく知られているように、賢治はのちに法華経に傾倒する。もし賢治と法華経の関係を無視したり軽視したりしている読者がいたとしたら、その賢治は日本人ではないのだろう。
たとえば『樺太鉄道』という詩に、「月光いろのかんざしは・すなほなコロボックルなのです・(ナモサダルマフンダリカスートラ)」と出てくる。この(ナモサダルマフンダリカスートラ)は、「妙法蓮華経」のサンスクリット読み「ナム・サダルマ・プンダリーカ・スートラ」である。この詩では何度もこのマントラが繰り返される。
賢治が法華経に傾倒するのは、在家仏教運動をおこし、日本精神を鼓吹した田中智学の法華経門に入ろうとしてからだった。その本拠が「国柱会」である。賢治が妹のトシの看病で東京に出たときに上野駅からまっすぐ向かったのが、田中智学のこの国柱会だった。
賢治が智学の法華精神論の虜になったことを論じている議論が極端に少ないのは、きっと賢治のような純粋きわまりない心情の持ち主に、戦闘的な青年仏教徒のイメージや法華国家主義のレッテルなど付与したくないからだろうが、ぼくなどはむしろそういう宮沢賢治だから、胸がつまるのである。
明治後期から大正時代にかけて、法華経を確信して生命の力を謳歌し、そこに国粋主義とアジア主義と世界主義とを加味して台頭した日蓮主義運動ともいうべきものがダイナミックに動いたことがある。その原点が田中智学と本多日生で、高山樗牛・姉崎正治が智学に感化されて最初に動いた。それがたちまち井上日召や北一輝や石原莞爾や牧口常三郎の思想の底辺になっていった。井上日召は一人一殺のテロリズムを唱え、牧口は創価学会を唱える。
賢治はそのような不穏な空気をのちにもたらした国柱会の入口を、あたかも青年が紅いネオンの奥の秘め事に魅かれるように、行ったり来たりしたのである。
なぜ、賢治は法華経に熱倒していったのか。

もともと「宮沢まき」の宗旨は浄土真宗で、出戻りの伯母ヤギから『正信偈』を子守唄のように聞いていた。『正信偈』はぼくも子供のころから歌うように読経させられた。
とくに賢治10歳のときに、大沢温泉に夏季仏教講習会のためにやってきた暁烏敏(あけがらす・はや)の世話を父親に命じられたときには、得意になってこの仏教改革者の身の回りにくっついていた。暁烏敏は、清沢満之に次いで近代浄土教に革新をもたらそうとした僧侶だが、その活動も精神もはなはだラディカルで、アナーキーだった。賢治にはどこか、このような革命家に一発で染まっていく気質があったようだ。が、だからこそ、宮沢賢治なのだ。
この夏季仏教講習会は父親が力を入れていたものらしく、記録を調べてみると、暁烏のほかに鈴木大拙や夏目漱石をゆすぶった釈宗演、近角常観、村上専精などの錚々たる仏教者が来ていた。中学になって盛岡に行くと、北山願教寺の仏教講習会に顔を出すが、ここでも島地大等の口吻に接していた。ここで島地の大きさにふれたことが、のちに島地編『漢和対照・妙法蓮華経』を読んだときの衝撃につながっていく。
もうひとつあまり知られていないことに、賢治の5年のときに担任が照井真臣乳に代わるのだが、この照井と斎藤宗次郎がかねてからの昵懇で、その縁で内村鑑三が花巻に来たときは宮沢家が内村にただならぬ敬意を払っていたことである。
賢治にクリスチャンの雰囲気があることは以前から指摘されていたが、この当時、ラディカル・ウィルの持ち主であるのなら法華経もキリスト教も国粋主義もその精神の裏地はまったく同じだったのだ。それは内村鑑三が『代表的日本人』に日蓮をあげていることでも、察せられよう。まあ、このことについてはこのくらいにしておく。
賢治は明治42年に盛岡中学校に入る。ここで「賢治の博物学」がめざめた。ナチュラル・ヒストリーにぞっこんになる。とくに鉱物採集と植物採集のためには方々を歩きまわっている。
金槌をもった登山にもあけくれた。岩手山には中学時代だけでも8回にわたって登頂した(生涯では30回を数える)。その南麓の小岩井農場に足を向けたのもこのときだ。童話『グスコーブドリの伝記』のイーハトーブ火山は岩手山である。
その名もずばりの『岩手山嶺』は、次のような詩句になっている。こんなふうに山を綴った山の詩人は他にいないのではないかというほどの絶顛を示していよう。
外輪山の夜明け方、
息吹きも白み競ひ立ち、
三十三の石神に、
米を注ぎて奔り行く。

北の脊梁山脈の精神をみごとに歌いあげている。こうして「賢治の博物学」は鉱物学、地質学、植物学、コロイド化学のほうに向かっていく。やがては自身がそこに身を投じて農業化学として結実したかったこの熱中は、もともとは“石っころ好き”に始まったものと思われる。賢治は子供の時分からみんなにそう呼ばれたような「石っこ賢さん」なのである。
それとともに、このころから短歌の試作が始まった。これもよくわかることで、鉱物と短歌、植物と俳句は、ほとんど同じ「切れ」なのである。とくに鉱物や植物を”標本”するということが、詩歌とりわけ短歌と俳句の取捨と選択の手法に近いのだ。ぼくも鉱物採集に熱中したときの俳句が一番際立っていた。賢治はこんな短歌である。
鳶いろのひとみのおくになにごとか
悪しきをひそめわれを見る牛
わが爪に魔が入り手ふりそそぎたる
月光むらさきにかがやき出でぬ
本堂の高座に島地大等の
ひとみに映る黄なる薄明
十秒の碧きひかりの去りたれば
かなしくわれはまた窓に向く
神楽殿のぼれば鳥のなきどよみ
いよよに君を恋ひわたるかも
3首目は島地大等の講演を聞いていたころの短歌。この「黄なる薄明」こそが法華経の光だった。
4首目は有名な「十秒の恋」といわれる歌で、賢治が大正4年に盛岡高等農林学校に入る直前に、発疹チフスの疑いで岩手病院に入院したときの歌。賢治は看護婦に片思いの初恋をした。この初恋の思いはあとをひき、その後も何度もこの片思いを偲ぶ詩や歌が詠まれた。入院時の青少年の感情というもの、よほどのことがないかぎりは看護婦に憧れる。
初恋に挫折し、病気が癒え、父が反対していた進学が許されると、賢治はいよいよ「立志の青年」になる。それまで学校の成績など気にもとめていなかった賢治も、盛岡農林学校では特待生であって、級長だ。賢治はすっかり変わっていた。
大正7年、22歳になっていた賢治に、鈴木三重吉の「赤い鳥」と武者小路実篤の「新しき村」が創刊されたニュースが伝わってきた。短編小説をいろいろ試みている一方、しだいに賢治の胸中に“新しい社会”が芽生えていたはずだ。
こうしてさきほど述べた大正10年、25歳の賢治は社会人として稗貫農学校の教師の職に就くことになり、生徒に向かって『精神歌』を作詞するという順番になる。農学校で賢治の創作はついに結晶化をおこす。『かしはばやしの夜』『注文の多い料理店』『春と修羅』の原型はここで醸成された。
この農学校の跡はいまは花巻市の文化会館になっている。ぼくも訪れた。そこに「ぎんどろ」(銀白楊)が植えてある。賢治が小さいころから大好きだった木であった。ここでは夕方に、あの『星めぐりの歌』が流れていた。こちらは作曲も賢治である。
ともかくも賢治を質朴派とか自然派とだけ捉えていたのでは、賢治はまったく見えてはこない。賢治はまさに十一面観音のように多様であり、かつルネサンス人のように多才だった。もし生涯がもっと長いものになっていたら、コロイド化学を大成していたかもしれず、農民革命をおこしていたかもしれない。
このへんで、ぼくのほうの賢治体験を書いておく。ぼくの賢治は中学時代に読んだ『風の又三郎』に始まっている。いまでもひょっとすると一番好きな童話かもしれない。
「どっどど・どどうど・どどうど・どどう」の音連れの風がもつ青い胡桃を吹き飛ばす感じ、さっとやって来てさっと去っていく正体のわからない転校生の感じ、木造小学校の窓ガラスががたがたとモリブデンのように哭く感じ、それらの寒いけれどもセピア色に調色された懐かしい印象は、中学の時に読んだままに、いまもってぼくを去らない。『風の又三郎』こそ日本の『スタンド・バイ・ミー』なのだ。
もっとも『風の又三郎』も複雑に再構成されて、ようやっと現状のかたちに仕上がった作品である。原型は奥羽北陸地方の“風の三郎様”の伝説にヒントを借りた「風野又三郎」というもので、これに「種山ケ原」や「さいかち淵」などの別の先行作品に黒インクで書きこんで手入れしたものをカット&ペーストし、さらにいくつもの紙片やノートにブルーブラックのペンで書きこんだ数々の一節をここへ盛りこみ、そのうえでまた削除した。
おそらくはまだ未完成であるらしく、現在も又三郎、三郎、一郎、孝一などの異同が混在したまま活字になっている。
衝撃をうけたのは高校生のときに開いた『春と修羅』だった。愕然として、どう言っていいかわからないほどだった。
それまでは萩原朔太郎や中原中也や富永太郎を読んでいて、「雨ニモマケズ」の賢治など詩人とは見えていなかったのに、そこから何もかもが賢治色になってしまったことを憶えている。ともかく「雲はたよりないカルボン酸」とか「花巻グランド電柱の百の碍子にあつまる雀」とか「アンドロメダも篝りにゆすれ・青い仮面のこけおどし」とか言われただけで、高校生のぼくは泣きそうになっていた。
それが「わたくしといふ現象は・仮定された有機交流電燈の・ひとつの青い照明です」の3行で明滅する賢治から発せられていると思うと、そのまま方晶化してしまいたかった。「おれはひとりの修羅なのだ」「まことのことばはここになく・修羅のなみだは土に降る」という覚悟も、ぼくの胸を騒がせた。
おそらく『春と修羅』は日本人が到達した近代詩集のなかで、最も高みに近づいたものではなかったか。
第1集の出版まもなくこれを読んで驚いた辻潤は、「この夏にアルプスに出掛けるなら『ツァラトゥストラ』を忘れても『春と修羅』を携へる」と書いた。これは心憎いばかりの褒め方だ。やはり第1集を読んだ若き草野心平は、「彼こそは日本始まって以来のカメラマンである、東北以北の純粋トーキーである」と感嘆した。そう、賢治はコロイド化学と銀塩化学に長じたカメラマンだったのだ。
が、それらのことについては『遊学』にもちょっと書いたし、また別の機会にゆっくり書きたいので、ここでは省く。『風の又三郎』がぼくの年来のお気にいりであることは、『遊』創刊号に書いた『ミトコンドリア・カルテット』を“高田又三郎”の筆名にしたことでも察してもらえるのではないかと思う。
むろん『春と修羅』も執拗な編集がされている。研究者たちは、最近では『春と修羅』の全体の配列がしだいに整うにしたがって、最後の手入れがそうとうになされたという見解をとる。
当然だ。推敲とは「推して、敲く」(引っぱり上げ、捨てていく)というところにあるけれど、それを賢治は二重三重どころか、つねに多重なものと心得ていた。これは賢治がナチュラル・ヒストリーに傾倒し、鉱物や岩石や化石の観察に異常な情熱を燃やし、しだいにコロイド化学の大成に向かっていったことと深い関係がある。賢治の推敲とは、あたかも化学組成の劇的な変則に似て、そのような言葉の微細な構成成分を、次々に代えて、元から変えて、さらには別の視線に替えて見ることだったのである。
第1集に「無声慟哭」という賢治らしい四字熟語の一連の詩が並んでいる。その『永訣の朝』は妹のトシとの永訣を歌った絶唱だが、その最終スタンザは、いまは次のようになっている。
おまへがたべるこのふたわんのゆきに
わたくしはいまこころからいのる
どうかこれが天上のアイスクリームになつて
おまへとみんなとに聖い資種をもたらすやうに
わたくしのすべてのさいはいをかけてねがふ
この4行は最初は2行だった。しかも「天上のアイスクリーム」のところは「どうかこれが兜卒の天の食に変つて」だった。兜卒の天は弥勒兜卒天浄土のことだが、それが「天上」になり、「食」が「アイスクリーム」になった。こういう推敲はいくらでもあった。
すでに「序」にして賢治自身がこう告白していたのだ。「これらは二十二箇月の・過去とかんづる方角から・紙と鉱質インクをつらね・ここまでたもちつづけられた・かげとひかりのひとくさりづつ・そのとほりの心象スケツチです」と。
心象スケッチというのは、賢治が「詩」という言葉を嫌って最期までこだわっていた自分の言葉の作品に与えていた用語である。
こういう“風又”“春修羅”派のぼくにも、やがて賢治を広く渉猟する日々がやってきた。アンデルセンを読んだときもそうであったように、ほとんどの賢治童話を連続して読んだので、ひとつずつの作品というよりも、そのイーハトーブ感覚の“内なる連鎖”に感染したといってよい。
この連鎖感覚は、けれども世間のイーハトーブ賛歌があまりにかまびすしいので、実はいったん凍結してしまっていた。あまりに美化されすぎた賢治はぼくの好みではなかったのだ。けれども、この連鎖感覚が実は晶洞(ゲオード)のような複雑で屈折的な内部をもっていて、そこに投じられた言葉のハイパートポロジカルな変容過程にこそコロイド賢治がいることに気がついたのは、さっきも書いたように、その後に厖大な異稿を含む筑摩書房の「校本宮沢賢治全集」に出会ったときからだった。
とくに、ノートやメモの数々を読んで、賢治の発想編集の現場が次々に見えてきたことは、ちょうど『遊』の編集にとりくもうとしているぼくに絶大なヒントを与えてくれた。たとえば、次のようなメモや草稿はかならずその奥でつながっている。
わがうち秘めし
異事の数 異空間の断片。
ぐっしょり寝汗で眼がさめて
鳴いているのはほととぎす
新月きみがおももちを
月の梢にかかぐれば
凍れる泥をうちふみて
さびしく恋ふるこころかな
結論。われらに要するものは銀河を包む透明な意志、
巨きな力と熱である。
われはダルケを名乗れるものと
つめたく最期のわかれを交はし
閲覧室の三階より
白き砂をはるかにたどるここちにて
その地下室に下り来り
一.異空間の実在。天と餓鬼。異構成―異単元。
幻想及夢と実在。
二.菩薩仏並に諸他八界依正の実在。
内省及実行による証明。
三.心的因果法則の実在。唯有因縁。
四.新信行の確立。
この残された推古時代の礎に
萱穂を二つ飾っておこう
それが当分
東洋思想の勝利でもある
最初のフレーズは「兄妹像手帳」のメモ、二つ目は『春と修羅』の異稿、3つ目と5つ目は文語未定稿から、次が『農民芸術概論』の最後の言葉、、6つ目は口語詩『東の雲ははやくも蜜の色に燃え』の下書き稿からとった。
最後の引用は『春と修羅』では「盗まれた白菜の根へ・一つ一つ萱穂を挿して・それが日本主義なのか」となっているもの。ここにあげたのはその草稿である。きわめて興味深い訂正が見える。このあたりに、賢治が田中智学にゆらぎながらも、結局は故郷の農村コロイド社会に踏みとどまれた弾力が見えてくる。しかしあとで述べるが、賢治自身はそうは思っていなかった。
どうも今夜が「千夜千冊」第900夜だということで、ついつい長く書きすぎたようだ。賢治について書きたいことなどいくらでもあるからそれでもいいが、これでは終わらない。では、もう一度、『銀河鉄道の夜』に戻ることにする。
まずもって、いままで伏せておいた最も大きな問題を指摘しておきたい。3つにわたる。
第1に、『銀河鉄道の夜』は長らく、「五、天気輪の柱」でジョバンニが草むらに寝っ転がって空を見ながら寝入って、その夢の中で銀河鉄道に乗る「六、銀河ステーション」になるのではなく、寝入ったあとに目が覚める場面が続いていた。
それが谷川徹三編の岩波文庫版で賢治の弟の宮沢清六氏の示唆により、「ジョバンニは目をひらきました。もとの丘の草の中につかれてねむっていたのでした」以下の旧版10ページほどを、「九、ジョバンニの切符」の最後の最後にもってきた。これは大きな変更だ。いまではこの構成が定番になっているのだが、どうしてこういうことがおこるかというと、賢治の草稿は、それも第4次の最終稿にも、まったくノンブル(頁付け)がなかったためである。
第2に、このように大きな構成が変更されたのだが、それでも、たとえば谷川徹三の岩波文庫版と、いま出回っている天沢退二郎編集の新潮文庫版では、細部が異なっている。とくにジョバンニが草むらで寝入るところは、ぼくには新潮文庫のほうがいい。ジョバンニのカムパネルラへの思いが滲み出ている。このあたりは読みくらべてもらうしかない。ようするに『銀河鉄道の夜』は未完成なのだ。
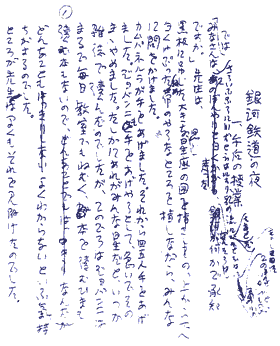
しかしいったい賢治はどう考えていただろうかというと、これが第3の指摘になるのだが、そもそも賢治の最初の構想では、ジョバンニが銀河鉄道の夢を見るのは、ブルカニロ博士の催眠術のせいだったのである。
そのため第1次草稿では、ジョバンニは銀河の旅の途中にいくども博士の「セロのような声」を聞く。そのうちカムパネルラが銀河列車から見えなくなると、ブルカニロ博士が「黒い大きな帽子をかぶった青白い顔の痩せた大人」の恰好で車内に出現し、不思議な地理と歴史の辞典を示しながら世界を解くというふうになっていた。
ところが賢治は、このブルカニロ博士の登場する場面をすべて削ってしまったのだ。ここでは言及できなかったのだが、ブルカニロ博士とは、30代の賢治が昭和になって「羅須地人協会」による農村文化の再生活動に邁進しようと決意したときの、賢治の胸の中にひそんでいた象徴的人格像なのだろうと思う。賢治はこのころ(つまり『銀河鉄道』の初期稿を書いていたころ)、借財をしてでも「労農芸術学校」を設立しようとさえ考えていた。が、地人協会の活動は挫折する。
こうして草稿『銀河鉄道』は、しばらくはジョバンニとカムパネルラの会話を中心の天体旅行だけになる。
けれどもふりかえれば、賢治は最初からジョバンニとカムパネルラの「少年の束の間の葛藤」を香ばしく描きたかったのである。そのため以降は、この二人の描写の重心をちょっとずつ変えていく。そして最後になってジョバンニの日々と劣等感が冒頭に加わって、そのぶんカムパネルラの行方を考えこんだ。
賢治が最終的にカムパネルラの不慮の死を想定したのは、以上の想像を絶する七転八倒の推敲編集の経緯からみると、考えられるかぎりの最も劇的な“悲劇の一撃”だったということになる。そのとたん、銀河鉄道のすべては世阿弥の橋懸かりのごとく、彼方に連なる蒼茫の鉄路となったのだ。
そして、このような結末に向かった賢治は、この作品を公刊することなく、昭和8年、肺結核を悪化して37歳で死んでいく。日本が満州国を建てて、これに酔いはじめた矢先のことだった。
さて、こうなると、『銀河鉄道の夜』は、ひょっとして賢治の「天路歴程」であったかと思えてくるし、また法華経に比するなら、これはさながらイーハトーブの「仮城喩品」なのかとも思えてくる。そう思うことも不可能ではない。
また、多くの識者がすでに言ってきたことだが、賢治はついに「他者」のために生き、「他者」のために死のうとしていたのではないかということも、見えてくる。ここはさまざまな仮説も可能なところであろう。
が、ぼくはここでほとんど知られていないことを示唆してみたい。それは、ある一通の手紙のなかに語られていた。
賢治は9月21日に、ちょうど風の又三郎が「雨はざっこざっこ雨三郎、風はどっこどっこ又三郎」とガラス戸に音をたて、誰も知らないうちに学校を去っていった日付に、ついに帰らぬ人となるのだが、その10日ほど前に、柳原昌悦宛にこんなふうに手紙を綴っていた。
なぜ、ここまで賢治が書いたのか、まことに悲痛なものがある。おそらくこれを読んで慟哭しない者は、いるまい。できるだけ静かに、ゆっくり読まれたい。
あなたがいろいろ想ひ出して書かれたやうなことは最早二度と出来さうもありませんが、それに代ることはきっとやる積りで毎日やっきとなって居ります。しかも心持ばかり焦ってつまづいてばかりゐるやうな訳です。
私のかういふやうな惨めな失敗はただもう今日の時代一般の巨きな病、「慢」といふうものの一支流に誤って身を加へたことに原因します。
僅かばかりの才能とか、器量とか、身分とか財産とかいふものが、何か自分のからだについたものででもあるかと思ひ、自分の仕事を卑しみ、同輩を嘲り、いまにどこからか自分を所謂社会の高みへ引き上げに来るものがあるやうに思ひ、空想をのみ生活して、却って完全な生活をば味ふこともせず、幾年かが空しく過ぎて漸く自分の築いてゐた蜃気楼の消えるのを見ては、ただもう人を怒り世間を憤り、従って師友を失ひ憂鬱病を得るといったやうな順序です。
これが宮沢賢治の最期の言葉なのである。壮烈に懴悔を超えて、すべての表現者や活動者に突き刺さる。とりわけ、「慢といふうものの一支流に誤って身を加へたことに原因します」は、痛いほどに強い響きを放っている。
「千夜千冊」第900夜。ぼくは宮沢賢治を世の幻想のままに放置しないためにも、拙いながらも以上のごとくに書いてみた。
言いたいことはまだまだあるけれど、一言でいうなら、宮沢賢治とは精神の極北における“編集化学の原郷”ともいうべきを、言葉のコンステレーションで示し続けようとした人だった。
けれども、その極北の編集化学の渦中に入って賢治を語るには、われわれはまだわれわれ自身の「慢心」にすら気づいていない。困ったことである。
すでに2番まで紹介した『精神歌』の4番は、次のような意味深長な歌詞になっている。こうなったらもはや、いつか気心の知れた面々と花巻・岩木あたりをめぐりたいと思うばかりになっている。ぼくだけでは賢治は語れない。道を踏むには一緒が、いい。
日は君臨し 輝きの
太陽系は真昼なり
険(けわ)しき旅の なかにして
われらは光の道を踏む
